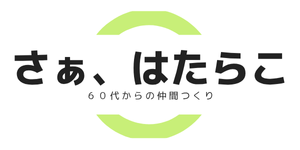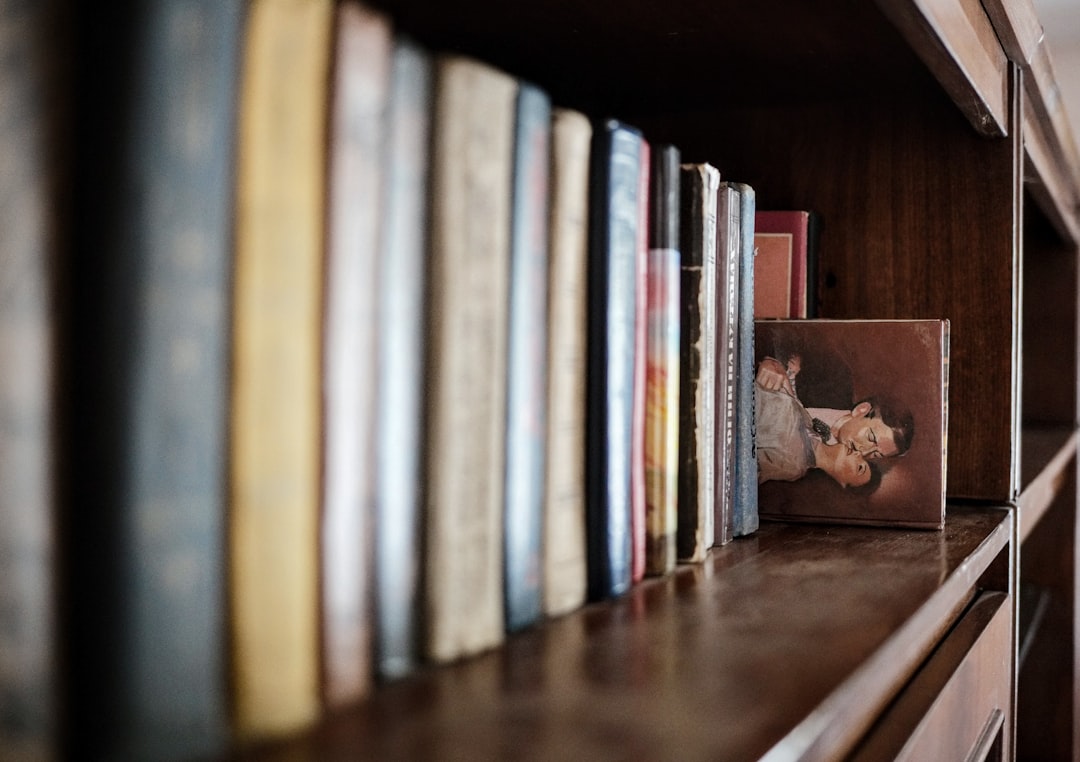40代の会社員である私、田中美咲は、最近父の様子がおかしいと感じていました。昔から倹約家ではありましたが、60代に入ってからの節約は、どうも度が過ぎているように見えたのです。
「これって普通なの?」父の異常な節約行動に募る不安
父の「節約」は、一般的なレベルをはるかに超えていました。一度使ったティッシュを捨てずに、まるで宝物のようにきれいに畳んで引き出しに溜め込んでいるのを見つけた時は、思わず息をのみました。部屋の電気は必要がないにもかかわらず異常なまでに消され、家中が薄暗い雰囲気。まるで電気代を払うことが、この世の終わりのように感じているかのようでした。最初は「年を取ったから、ちょっと変わったのかな」と軽く考えていたのですが、日を追うごとにその行動はエスカレートしていきました。
「このままだと、お父さん、本当にどうなっちゃうんだろう…」。私の心には、漠然とした不安が募っていきました。「ただの頑固な節約癖じゃない、もっと深い何かが隠れている気がする」。家族で話し合っても、「昔ギャンブルで苦労した反動だろう」という声は出るものの、具体的な解決策は見つからず、ただ心配するばかり。父に直接注意すれば、怒り出すか、逆にふてくされてしまうのが常でした。もうダメかもしれない…、こんなはずじゃなかった…と、私は一人で抱え込んでいました。
心理カウンセラーの友人・健太に相談して見えた「心のサイン」
そんな時、私は学生時代からの親友で、現在は臨床心理士として働く佐藤健太に連絡を取りました。カフェで会うなり、私は父の様子を必死に伝えました。
私:「ねえ、健太。うちの父のことなんだけど、最近、節約がどうも行き過ぎてる気がして。一度使ったティッシュを捨てずに溜め込んだり、必要以上に電気を消したり…」
健太:「うん、話してみて。それは心配になるよね。節約行動の背景には、いくつか考えられることがあるんだ。例えば、過去の経験からくる強い不安や、認知機能の変化、あるいは強迫的な傾向が関係している場合もあるよ」
健太の言葉に、私はハッとしました。
私:「やっぱりそうなんだ…。昔、ギャンブルで苦労した時期があったから、その反動なのかなって…」
健太:「その可能性は十分にあるね。過去のトラウマや経済的な困窮経験が、高齢になってから過度な節約行動として現れるケースは少なくないんだ。特に、ギャンブルでの失敗は、経済的な不安を強く心に刻むからね。それが強迫性障害やうつ病、認知症の初期症状として現れることもあるんだよ」
健太は、父の行動は単なる「節約癖」ではなく、心の奥底に潜む「不安」や「恐れ」、あるいは精神的な病気のサインかもしれないと教えてくれました。そして、頭ごなしに否定するのではなく、まずは父の行動の背景にある感情に寄り添うことが大切だとアドバイスしてくれたのです。
家族が気づくべき異常な節約行動のサインと適切な接し方
健太との話を通じて、私は父の行動に対する見方を大きく変えることができました。単なる「変な人」ではなく、「何かに苦しんでいる人」として父を見るようになったのです。健太は、家族が気づくべきサインと、その際の適切な接し方について、具体的なアドバイスをくれました。
異常な節約行動のチェックリスト
以下のような行動が見られたら、単なる節約癖ではない可能性があります。
- 過度な収集癖: 一度使ったものを捨てられない、あるいは不要なものを異常に溜め込む。
- 社会生活への支障: 節約のために外出を控える、人との交流を避けるなど、生活の質が著しく低下する。
- 精神的な苦痛: 節約できないことに対して強い不安や罪悪感を覚える。
- 家族との衝突: 節約法を巡って家族と頻繁に口論になる。
- 衛生面の問題: 節約のために清潔感を損なう行為がある(例:入浴を極端に控える)。
家族ができること:共感と専門家への相談
健太が最も強調したのは、「共感」と「専門家への相談」でした。
1. 頭ごなしに否定しない: 「なぜそんなことをするの?」と問い詰めるのではなく、「何か不安なことがあるの?」と、父の気持ちに寄り添う姿勢を見せること。
2. 傾聴の姿勢: 父が話したがる時は、遮らずに最後まで耳を傾ける。行動の裏にある「本当の理由」を探る手助けをする。
3. 安心できる環境づくり: 経済的な不安を感じている場合、具体的な数字を示して「生活は大丈夫だ」と安心させる。
4. 専門家への相談: もし、家族だけでは対応が難しいと感じたら、迷わず精神科医や心療内科、地域の保健センターなどに相談すること。早期の専門的なサポートが、本人と家族の負担を軽減します。
健太は「家族だけで抱え込まず、第三者の力を借りる勇気を持つことが、何よりも大切だよ」と力強く言ってくれました。
よくある質問
Q1: 父が病院に行くのを嫌がります。どうすればいいですか?
A: まずは家族だけで専門機関(地域の保健センターや精神保健福祉センターなど)に相談し、状況を説明してアドバイスをもらいましょう。直接病院に行かなくても、専門家が自宅訪問や電話での相談に応じてくれるケースもあります。
Q2: 節約の話をすると怒り出すのですが、どうしたらいいですか?
A: 節約の話は避け、まずは日常の会話で信頼関係を築くことに注力しましょう。「いつもありがとう」「助かるよ」といった感謝の言葉を伝えることで、孤立感を和らげる効果が期待できます。その上で、少しずつ「何か困っていることはない?」と優しく尋ねてみてください。
Q3: 高齢者の節約は、認知症のサインなのでしょうか?
A: 認知症の初期症状として、金銭感覚の変化や収集癖が見られることがあります。しかし、必ずしも認知症とは限りません。過去の経験や精神的な要因も考えられます。自己判断せず、専門医の診断を受けることが重要です。
心の健康は、何よりも大切な「財産」
父の異常な節約行動は、最初は私にとってただの「困った癖」でした。しかし、心理カウンセラーの健太に相談し、それが父の心のSOSである可能性を知ってからは、見方が大きく変わりました。過去の苦い経験が、父の心を縛り付けていたのかもしれない。そう思うと、胸が締め付けられるようでした。
私たちの家庭は、まだ解決の道のりの途中です。しかし、父の行動の背景を理解し、頭ごなしに否定するのではなく、寄り添う姿勢を持つことで、少しずつですが父との関係性も変化してきました。健太が言ったように、心の健康は、どんなお金にも代えがたい大切な「財産」です。もし、あなたの家族も同じような悩みを抱えているなら、どうか一人で抱え込まないでください。まずは家族で話し合い、そして必要であれば、迷わず専門家の力を借りてみてください。その一歩が、家族の未来を明るく照らす光となるはずです。
この記事を書いた人
田中 美咲 | 40代 | 家族の心の健康に関するテーマを得意とするwebライター
自身の家族の経験から、高齢者の心のケアや家族間のコミュニケーションの重要性を痛感。読者が抱えるデリケートな悩みに寄り添い、具体的な解決策と希望を伝える記事執筆を目指しています。