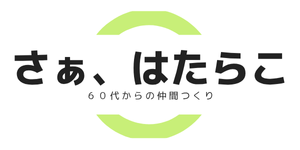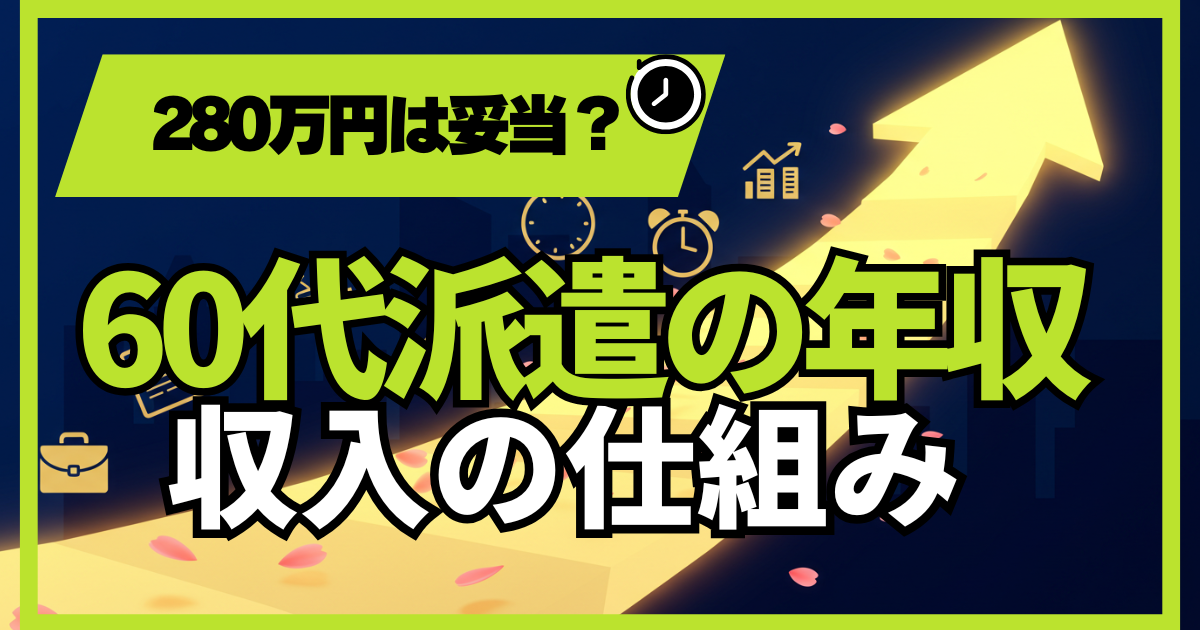「年金だけでは足りない」── そう信じて始めた派遣が、想像以上に厳しかった
深夜、私は台所のテーブルで給与明細を握りしめていました。
手取り17万4,000円。
時給1,200円で週5日、1日7時間。計算すれば月20万円近くになるはずが、社会保険料と税金で約5万円が消えていました。
「現役時代は年収600万円だったのに…」
夫を早くに亡くし、年金は月12万円。娘には「大丈夫」と言ってきた手前、今さら援助は頼めない。通帳の残高は毎月じりじりと減っていく。このままでは、5年後には貯金が底をつく計算です。
これが、62歳の私、鈴木美代子の現実でした。
もしかしたら、あなたも同じような不安を抱えているのではないでしょうか。
- 「60代の派遣って、みんなこんなに収入が低いの?」
- 「もっと良い条件で働けるのでは?」
- 「でも、この年齢で文句を言えない…」
実は私も、最初の半年間は「年齢的に仕方ない」と諦めていました。
しかし、派遣会社の担当者との何気ない会話から、私が知らなかった「収入の仕組み」があることに気づいたのです。それを理解してから、私の状況は少しずつ変わり始めました。
今日は、私が半年かけて学んだ「60代派遣の収入のリアル」と、知っているだけで条件が変わる重要な知識をお伝えします。
絶望から始まった私の「派遣」という働き方
「派遣なら簡単に仕事が見つかる」── そう思っていた
60歳で再雇用の打診を断り、派遣を選んだのは「自由に働けそう」という淡い期待からでした。
派遣会社に登録したのは3社。大手2社と、友人が紹介してくれた地域密着型の会社です。担当者は皆、丁寧に対応してくれました。
「鈴木さんのご経験なら、すぐに良いお仕事が見つかりますよ」
その言葉を信じて、私は週5日・フルタイムの事務職を希望しました。経理経験30年。エクセルもワードも使える。これなら需要があるはずだ、と。
でも現実は、想像以上に厳しかった
最初に紹介された仕事は、時給1,050円の軽作業でした。
「え…経理じゃなくて?」
「はい、経理は若い方の応募が多くて…まずはこちらで実績を作られては」
結局、3ヶ月待って見つかったのが、今の一般事務。時給1,200円。現役時代の経験は、ほとんど評価されませんでした。
最初の給与明細を見たとき、画面が霞んで見えました。
総支給額233,000円から、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税…次々と引かれていく。最終的に振り込まれたのは17万4,000円。
「これで、家賃も食費も払って、医療費も貯金も…?」
その夜、私は娘に電話をかけそうになりました。でも、指が動きませんでした。
ハローワークに通い、求人サイトを漁る日々 ── でも、何も変わらなかった
「もっと良い条件があるはずだ」と必死に探した
翌週から、私は毎週ハローワークに通いました。
シニア向けの求人を片っ端からチェックし、気になるものには全て応募しました。でも、返事が来るのは3割程度。面接まで進んでも「若い方に決まりました」という連絡ばかり。
求人サイトも毎日チェックしました。「60代歓迎」「シニア活躍中」の文字を見つけると、すぐに応募。でも、実際に話を聞くと時給1,100円だったり、週3日しか働けない条件だったり。
3ヶ月間、20社以上に応募して、面接は5回。全て不採用でした。
周囲に相談しても、答えは同じだった
「60歳過ぎたら、そんなもんよ」
「年金もらえるだけマシじゃない」
「贅沢言わずに、働けるだけありがたいと思わなきゃ」
友人たちは皆、そう言いました。確かに、仕事があるだけ恵まれているのかもしれない。でも、心のどこかで「本当にそうなのか?」という疑問が消えませんでした。
私が間違っているのか、それとも、私の知らない「何か」があるのか。
答えが見つからないまま、ただ時間だけが過ぎていきました。
転機は、派遣会社の担当者との「何気ない会話」から始まった
「鈴木さん、マージン率って知ってます?」
契約更新の面談のとき、担当の山田さん(仮名)が何気なくそう聞いてきました。
「マージン率…ですか?」
「ええ。派遣会社が企業からもらう金額と、鈴木さんに支払う時給の差のことです」
正直、私は派遣会社が「ピンハネ」していると思っていました。だから、あまり良い印象はありませんでした。
でも山田さんの説明は、私の認識を完全に覆すものでした。
「実は、派遣会社の利益って…」
山田さんはタブレットで資料を見せてくれました。
「企業が当社に支払う金額が、例えば時給1,800円だとします。そのうち鈴木さんに支払うのが1,200円。差額の600円、つまり約33%がマージンです」
「やっぱり、そんなに取るんですね…」
私の表情を見て、山田さんは苦笑しながら続けました。
「でも、この600円の内訳を見てください」
- 社会保険料(会社負担分): 約200円
- 有給休暇の費用: 約75円
- 営業・サポート費用: 約245円
- 会社の利益: わずか約20円
「え…利益って、そんなに少ないんですか?」
「そうなんです。派遣会社の営業利益率は、業界平均で約1.2%。ほとんどが鈴木さんの保険や福利厚生、私たちのサポート費用に使われているんですよ」
その瞬間、私の中で何かが変わりました。
派遣会社は敵ではない。むしろ、うまく使えば味方になる。そう気づいたのです。
そこから始まった、私の「学び」の日々
「なぜ、同じ60代でも収入が違うのか?」
山田さんとの会話をきっかけに、私は徹底的に調べ始めました。
図書館で派遣や労働に関する本を借り、ハローワークの相談員に何度も質問し、同年代の派遣仲間にも話を聞きました。
そこで分かったのは、60代派遣の収入には明確な「法則」があるということでした。
【衝撃の事実1】年収280万円は「標準」だった
厚生労働省のデータによると、60~64歳の派遣労働者の平均年収は279万円。
つまり、私の年収280万円は、決して低いわけではなかった。むしろ、ほぼ平均値だったのです。
| 年齢層 | 平均年収 |
|---|---|
| 50~54歳 | 282万円 |
| 55~59歳 | 318万円 |
| 60~64歳 | 279万円 |
| 65歳以上 | 244万円 |
ただ、ここで重要なのは「なぜ60歳で収入が下がるのか」という理由でした。
【衝撃の事実2】「収入の崖」は個人の問題じゃなかった
60歳定年後の再雇用で、賃金が定年前の約78.7%に減少する。これは「収入の崖」と呼ばれる、日本の雇用制度に組み込まれた構造的な現実です。
つまり、私が「能力が評価されない」と感じていたのは、個人の問題ではなく、社会全体の仕組みが原因だったのです。
この事実を知って、私は少し楽になりました。
「自分が悪いわけじゃない」── そう思えただけで、前を向く力が湧いてきたのです。
知識を武器に、私は動き始めた
戦略1: 複数の派遣会社を「使い分ける」
山田さんからのアドバイスで、私は新たに2社の派遣会社に登録しました。
- 専門特化型: 経理・財務に強い派遣会社
- シニア特化型: 60代の雇用実績が豊富な会社
すると、驚くことに、同じ経理事務でも時給が200円以上違う案件が見つかりました。
「え、こんなに差があるの…?」
それまでの私は「派遣会社はどこも同じ」と思っていました。でも実際には、会社によって得意分野も、持っている案件も全く違ったのです。
戦略2: 「60歳以上の特権」を知る
60歳以上の派遣には、「3年ルールの適用除外」という法的な優遇措置があります。
通常、派遣社員は同じ職場で3年以上働けません。でも、60歳以上はこのルールが適用されないため、長期的に安定して働けるのです。
これは企業にとっても大きなメリット。
面接で「私は3年ルールの対象外なので、長期的にお役に立てます」と伝えると、採用担当者の表情が明らかに変わりました。
戦略3: 「65歳」という重要な境界線
調べていて気づいたのは、65歳を境に社会保険料が大きく変わるということです。
| 項目 | 60~64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 約11,400円 | 約11,400円 |
| 介護保険料 | 約1,900円 | 約1,900円 |
| 厚生年金保険料 | 約21,400円 | 対象外 |
| 雇用保険料 | 約1,300円 | 対象外 |
| 合計 | 約36,000円 | 約13,300円 |
つまり、同じ時給でも、65歳以降は月2.3万円、年間約27万円も手取りが増えるのです。
「あと3年頑張れば、自動的に収入が上がる…」
この事実を知って、私は初めて希望を感じました。
そして今、私の状況は少しずつ変わっている
時給1,200円 → 1,400円への道のり
専門特化型の派遣会社で、月次決算をサポートする仕事が見つかりました。
時給1,400円。週5日・1日7時間で、月収は約22万円。手取りでも約18.7万円になります。
年収にすると約310万円。
平均の279万円より、約30万円多い計算です。
もちろん、これで全てが解決したわけではありません。でも、少なくとも「貯金が減り続ける恐怖」からは解放されました。
「知っているか、知らないか」── それだけの差だった
振り返ると、私が変えたのは「職種」と「派遣会社の使い方」、そして「自分の市場価値の伝え方」だけです。
能力が上がったわけではありません。ただ、収入の仕組みを理解し、戦略的に動いた。それだけです。
でも、その「知識」を持っているかどうかで、年収が30万円以上変わる。
これが、60代派遣の現実なのです。
あなたが今日から使える「収入改善の具体策」
今すぐできること
① マージン率を確認する
全ての派遣会社は、マージン率を公開する義務があります。派遣会社のウェブサイトで確認してください。
透明性の高い会社を選ぶことが、第一歩です。
② 複数の派遣会社に登録する(推奨3~4社)
- 大手総合派遣会社: 1~2社(安定案件)
- 専門特化派遣会社: 1社(高単価)
- シニア特化派遣会社: 1社(理解ある環境)
③ 「60歳以上の強み」を面接で明確に伝える
「私は3年ルールの対象外なので、長期的に安定して働けます」
「30年の経理経験があるため、即戦力として貢献できます」
年齢を弱みではなく、強みとして提示する。
中期的に取り組むこと
① 教育訓練給付制度を使う
国の制度で、スキルアップ講座の受講費用を最大70~80%補助してもらえます。
- ITスキル
- 専門的な会計知識
- 介護福祉士
高収入に直結する資格を、大幅な自己負担軽減で取得できます。
② 契約更新時に時給交渉をする
1年間の実績をまとめ、具体的な貢献を資料化してください。
「皆勤賞」「新人指導」「業務改善提案」など、数字で示せるものがベストです。
市場相場との比較も忘れずに。「同職種の平均時給より100円低い」といった根拠があれば、交渉しやすくなります。
「諦めなければ、道は開ける」── 私が伝えたいこと
最初、私は「年齢的に仕方ない」と諦めていました。
でも、知識を得て、動き始めたことで、状況は確実に変わりました。
もちろん、現役時代と同じ年収600万円には戻れません。それは現実として受け入れる必要があります。
でも、平均を上回る条件で働くことは、決して不可能ではありません。
- 職種を戦略的に選ぶ
- 派遣会社を使い分ける
- 自分の市場価値を正しく伝える
- 公的支援制度を活用する
これらを組み合わせるだけで、年収は30~50万円変わります。
そして何より大切なのは、「自分で選択している」という感覚を取り戻すことです。
65歳という「希望の境界線」
私はあと3年で65歳になります。
その時、社会保険料が年間約27万円減ることで、手取りは自動的に増えます。同じ時給1,400円でも、年収は実質340万円相当になる計算です。
「あと3年」── そう思うと、今の仕事も前向きに捉えられます。
最後に: あなたへのメッセージ
もしあなたが今、給与明細を見て落胆しているなら。
もしあなたが「この年齢では仕方ない」と諦めかけているなら。
まだ、終わりではありません。
私も62歳から学び、動き始めました。あなたにも、まだ時間はあります。
この記事が、あなたの「最初の一歩」になれば幸いです。
📚 参考文献・データ出典
本記事で使用している統計データ・制度情報は、以下の公的機関および信頼できる情報源に基づいています:
統計データ
- 厚生労働省「雇用の構造に関する実態調査」(2024年版)
- 年齢別派遣労働者の平均年収データ
- 60歳定年後の賃金減少率(78.7%)
- 一般社団法人日本人材派遣協会「派遣労働者実態調査」(2023年度)
- 派遣料金の内訳とマージン率
- 職種別平均時給データ
制度・法律関連
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
- 労働者派遣法関連資料
- 60歳以上の3年ルール適用除外規定
- 派遣会社のマージン率公開義務
- 日本年金機構
- 社会保険料率(健康保険・厚生年金)
- 65歳以上の保険制度変更点
その他
- ハローワークインターネットサービス
- シニア向け求人情報
- 65歳超雇用推進助成金